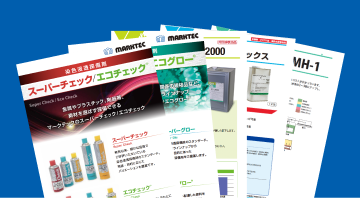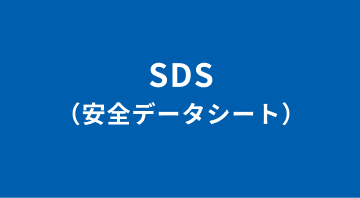- 非破壊検査・印字マーキング
磁粉を試験対象に適用する方法について
磁粉探傷試験ではきずに磁粉を吸着させるため、試験面上に磁粉を均一に散布(適用)することが重要です。
試験対象や検査環境に応じて、適切な磁粉の適用方法を設定する必要があります。
磁粉の適用方法
適用方法は大きく「湿式法」と「乾式法」に分けられます。
湿式法
液体に磁粉を分散させた検査液(磁粉液)を調製して使用する。
- 複雑形状の試験面にも磁粉を均一に適用でき、適用状態の把握も容易。
- 試験操作が容易で試験結果が安定しやすい。
- 検査液(磁粉液)の状態や性能について定期的な管理が必要。
- 試験対象が液体で濡れるため分散媒に応じた後処理が必要。
乾式法
粉体そのままの磁粉を使用する。
- 溶接開先面などの高温部分や液濡れをきらう試験対象の検査ができる。
- 試験対象の内部のきずへの感度が比較的高い。
- 粉体のため試験条件を安定させづらく、結果がばらつきやすい。
- 精密な検査や複雑な形状の試験対象の検査にはむかない。
湿式法の種類
「湿式法」で磁粉を分散させる液体について、試験内容に適したものを選定することで、試験の効率や精度を改善できる場合があります。
水を用いる「水分散」
調達の容易さやコスト、安全性の面から、よく採用される方法。水を用いるため、試験対象の錆の発生にについて注意が必要。
灯油などの液体油を用いる「油分散」
試験対象に対する錆の発生がない。引火性液体を用いるため、消防法等の管理が必要となる。
検査液(磁粉液)の調製について
湿式法の磁粉探傷試験において、検査液(磁粉液)の状態は試験結果に大きく影響を与えます。
特に検査液に含まれる磁粉の量(磁粉液濃度)は重要で、試験対象や検出したいきず、適用する磁粉などで試験に適した磁粉液濃度は異なります。お客様にて有効な検査結果の得られる磁粉液濃度の範囲を確認し、管理することを推奨します。
また、検査液中の磁粉が均一に分散していることも重要です。磁粉がダマになりやすい水分散の検査液を調製する場合は、以下を参考に検査液を調製してください。
粉体タイプ磁粉の検査液調製方法(スーパーマグナ LY-10~40など)
粉末磁粉+液体タイプの分散剤(BC-700、EC-4など)の場合
- 粉と分散剤をそれぞれ小容器に計量します。
- 磁粉に分散剤を少量ずつ入れながら 、かくはん棒などでよく練ってペースト状にします。
- タンクの水をかくはんしながら、ペーストを少量ずつ投入します。
- 小容器内に付着したペーストはタンクの水で共洗いして、タンクへ投入します。
- 5~10分後、 検査液の懸濁を確認して 検査を開始します。
磁粉濃縮液(Conc.)タイプの検査液の調製方法(エコマグナ LY-10~40 Conc.)
- エコマグナLY-Conc.の容器を上下によく振り、小容器に計量します。
- タンクの水をかくはんしながらエコマグナLY-Conc.を投入します(小容器に付着したLY-Conc.はタンクの水で共洗いして、タンクへ投入します)
- 5~10分後、 検査液の懸濁を確認して 検査を開始します。
※LY-Conc.で検査液を調製する際は下表を参考に磁粉液濃度に応じた量を投入してください。
<検査液の調整例(100Lの場合)>

- STEP
100Lの水に濃縮磁粉液を500mL入れます。

- STEP
かくはんをすることで、均一な磁粉液(濃度:1.0g/L)に調製できます。
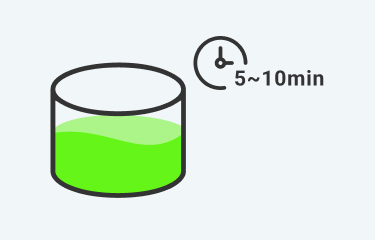
- STEP
5~10分後、磁粉液の縣濁を確認し、検査を開始してください。